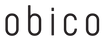■ 西陣|唐織|花車文 ■
この帯に描かれている柄・文様
Japanese patterns and motifs used in this obi

菊
Chrysanthemum
日本の花というイメージが強い菊ですが、奈良時代から平安時代にかけて中国から渡ってきたといわれています。ほどなくして宮中行事に用いられるようになり、南北朝時代には皇室の御紋となりました。格式ある日本の秋の花というイメージは、長い歴史の中で培われてきたものなのです。

御所車
Imperial Cart
平安時代の貴族の乗り物で「源氏物語」の世界を象徴するもので「源氏車」とも呼ばれます。
特に御所の風景を表現した御所解き文様や源氏物語絵巻のモチーフとして華やかな風情を添えて描かれることが多い文様です。

牡丹
Peony
幸福、富貴、高貴を象徴する「百花の王」牡丹は、平安時代から着物の紋様として用いられてきました。単体のモチーフだけでなく、室町時代から近世に至るまで多くの人に好まれた、唐草と組み合わせた「牡丹唐草文様」など、さまざまな形で表現されてきた植物です。

梅
Plum blossom
奈良時代のはじめに中国から渡ってきた梅は、厳寒の中いち早く花を咲かせることから、忍耐力や生命力を象徴する花として愛好されてきました。学問の神様、菅原道真公が梅の歌を詠んだことから、天満宮の社紋にも用いられています。
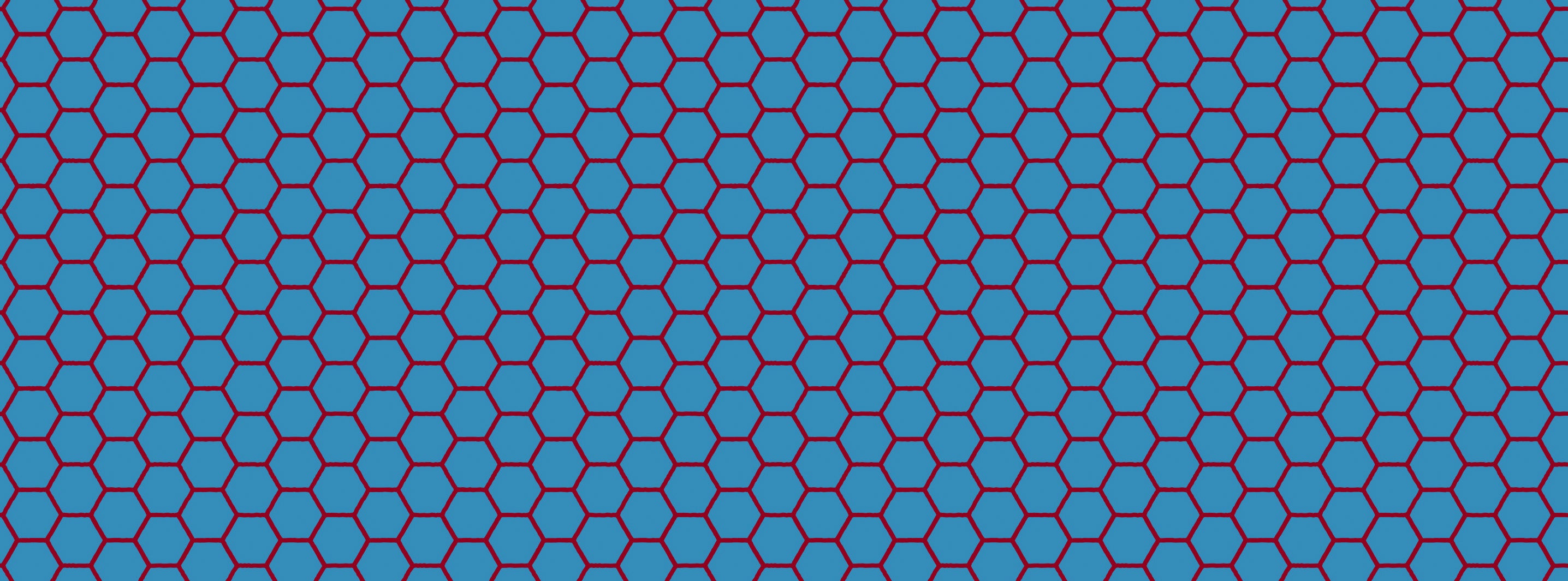
亀甲
Tortoise Connection
西アジアが起源で、中国や朝鮮から日本に伝えられたといわれています。元々は幾何学文様ですが、東洋に渡った後に亀の甲羅に似ていることからこの名が付けられたようです。