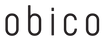■ 西陣|唐織|御所車花文|九百錦|プラチナ二重箔 ■
この帯に描かれている柄・文様
Japanese patterns and motifs used in this obi

菊
Chrysanthemum
日本の花というイメージが強い菊ですが、奈良時代から平安時代にかけて中国から渡ってきたといわれています。ほどなくして宮中行事に用いられるようになり、南北朝時代には皇室の御紋となりました。格式ある日本の秋の花というイメージは、長い歴史の中で培われてきたものなのです。

牡丹
Peony
幸福、富貴、高貴を象徴する「百花の王」牡丹は、平安時代から着物の紋様として用いられてきました。単体のモチーフだけでなく、室町時代から近世に至るまで多くの人に好まれた、唐草と組み合わせた「牡丹唐草文様」など、さまざまな形で表現されてきた植物です。

萩
Bush clover
夏の終わり頃に淡い紅色や白色の小さな花をたくさんつける、全国各地の山野で見ることができる植物です。花、葉、枝を図案化した文様が一般的で、花は3房に、丸い葉は3つの小葉に分かれるという形状の特徴が表現されています。

菖蒲
Iris
かつては「あやめ」の呼び名が一般的でしたが、葉の形が似ている芳香と厄よけの植物「菖蒲」の字をあててから、この名で呼ばれるようになったようです。杜若とよく似ていますが、花びらの元の部分が白いのが杜若、黄色い筋が入っているのが菖蒲です。
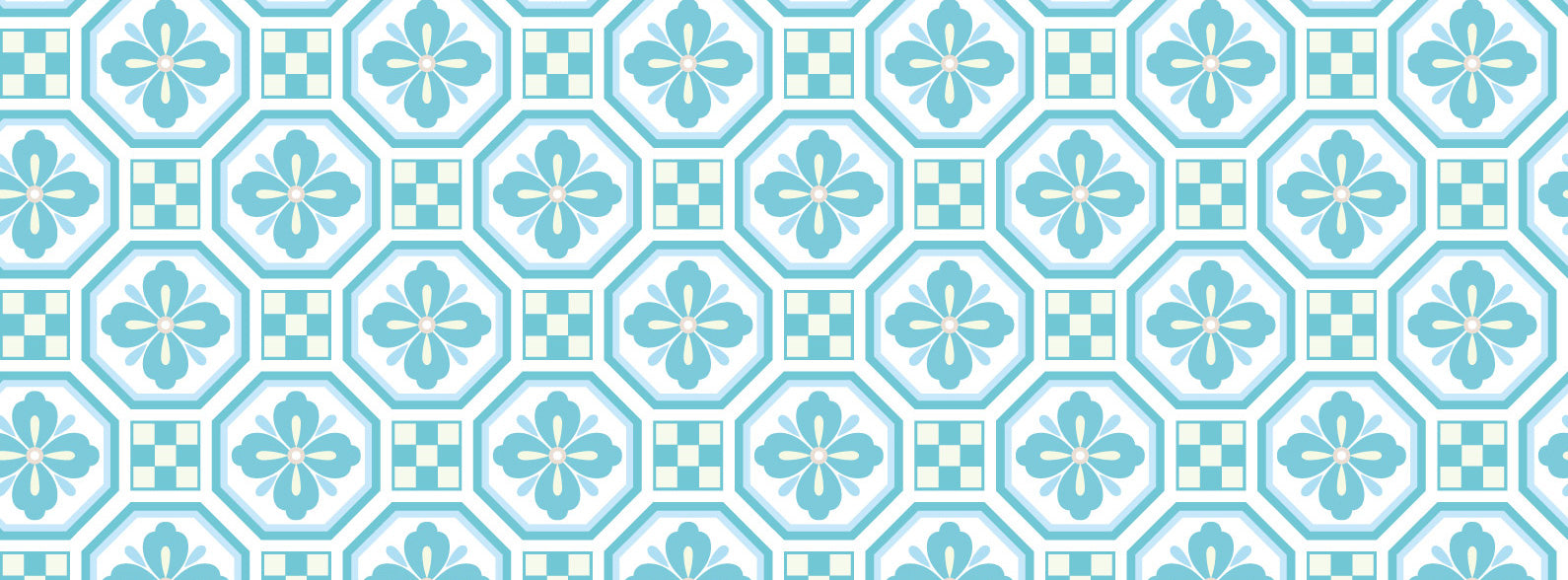
蜀江
Octagonal Square
3世紀頃に中国で栄えた、蜀国の首都を流れていた川の名を冠した割付文様。流域で織られていた赤い地色の錦「蜀江錦」に、原型となる文様が使われていたことから、この名が付けられたと考えられています。
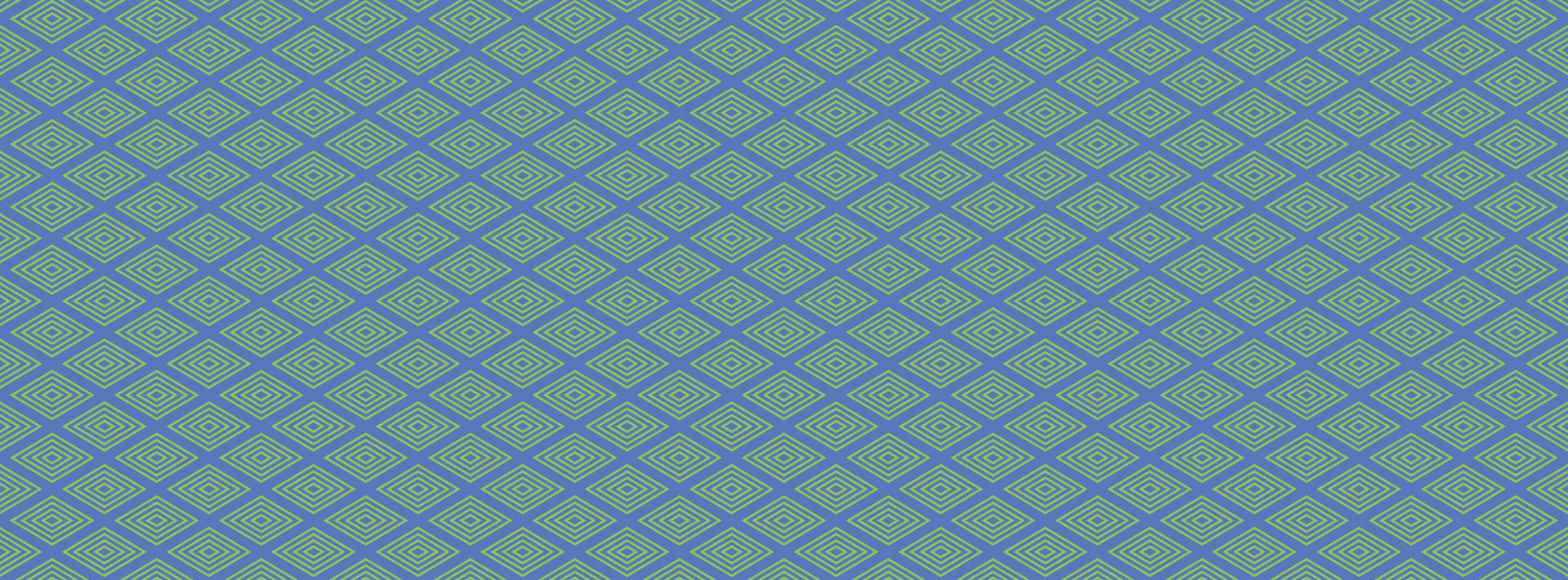
菱
Diamonds
縄文時代の土器にも刻まれるなど古くから描かれてきた文様で、平安時代に有職文様として公家装束に用いられるようになり一気に広まったと考えられています。連続して配した「斜め格子」や「襷文様」、羽を広げた鶴が向かい合い菱形をつくる「向い鶴菱」、4つの菱形で構成された「四菱」など、多様な表現を見ることができます。