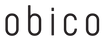この帯に描かれている柄・文様
Japanese patterns and motifs used in this obi

菊
Chrysanthemum
日本の花というイメージが強い菊ですが、奈良時代から平安時代にかけて中国から渡ってきたといわれています。ほどなくして宮中行事に用いられるようになり、南北朝時代には皇室の御紋となりました。格式ある日本の秋の花というイメージは、長い歴史の中で培われてきたものなのです。

唐草花
Chinese flower and plant vines
日本には古墳時代に中国から伝わったとされていますが、ギリシャやローマの連続文様「パルメット」がルーツという説もあります。地を這うように伸びる蔓が、強い生命力を発揮するとして尊ばれ、松や菊や梅など、蔓を持たない植物にもアレンジされ発展してきました。

牡丹
Peony
幸福、富貴、高貴を象徴する「百花の王」牡丹は、平安時代から着物の紋様として用いられてきました。単体のモチーフだけでなく、室町時代から近世に至るまで多くの人に好まれた、唐草と組み合わせた「牡丹唐草文様」など、さまざまな形で表現されてきた植物です。

ヱ霞
エHaze
霞文様よりも、デフォルメして霞を表現した文様。中に季節の草花を入れたもの、松竹梅や宝尽くしなどの吉祥文様を入れた表現もよく見られます。また、横長のふくらみのあるものを4つつなげたものは「春霞文」と呼ばれます。
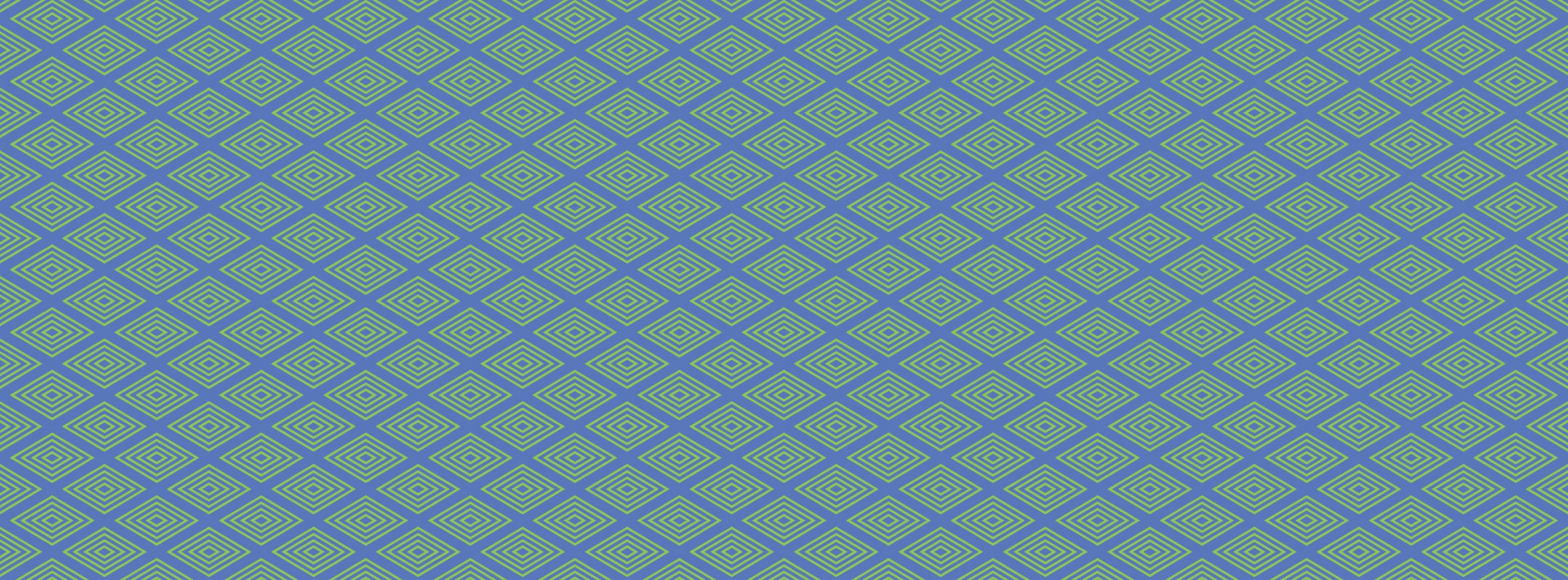
菱
Diamonds
縄文時代の土器にも刻まれるなど古くから描かれてきた文様で、平安時代に有職文様として公家装束に用いられるようになり一気に広まったと考えられています。連続して配した「斜め格子」や「襷文様」、羽を広げた鶴が向かい合い…