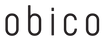■ 唐織|流木鴛鴦文|九百プラチナ箔 ■
この帯に描かれている柄・文様
Japanese patterns and motifs used in this obi

菊
Chrysanthemum
日本の花というイメージが強い菊ですが、奈良時代から平安時代にかけて中国から渡ってきたといわれています。ほどなくして宮中行事に用いられるようになり、南北朝時代には皇室の御紋となりました。格式ある日本の秋の花というイメージは、長い歴史の中で培われてきたものなのです。

牡丹
Peony
幸福、富貴、高貴を象徴する「百花の王」牡丹は、平安時代から着物の紋様として用いられてきました。単体のモチーフだけでなく、室町時代から近世に至るまで多くの人に好まれた、唐草と組み合わせた「牡丹唐草文様」など、さまざまな形で表現されてきた植物です。

流水
Running water
着物や帯に描かれる流水は、多くが小川を表していると考えられていますが、一方で、一滴の水が海に注ぐまでを人生に見立てるなど、多様な表現を見ることもできます。「茶屋辻」や「御所解き文様」などの風景文様、「杜若」や「菖蒲」など、流水との組み合わせが定番となっている文様は数多くあります。

鴛鴦
Mandarin duck
日本には「おしどり夫婦」という言葉がありますが、中国でも同様に夫婦の変わらぬ愛を象徴する鳥である鴛鴦。桃山時代から江戸時代あたりの能装束や小袖に多く見られる紋様です。ちなみに漢字では、雄を鴛、雌を鴦と書き分けます。