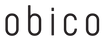この帯に描かれている柄・文様
Japanese patterns and motifs used in this obi

唐花
Chinese flower
中国から伝えられた花文様であることから、この名がつけられました。空想の花をモチーフとして飛鳥時代から奈良時代にかけて発達し、5弁から8弁にまとめて和風にアレンジされたのが平安時代頃と考えられています

鳳凰
Phenix
古代中国で、龍・亀・麒麟と並び四瑞と称された、めでたいときにやってくる天の使いである鳳凰。日本で文様として使われるようになったのは飛鳥時代で、中国から伝わった鳳凰文を基本に、工芸品などに描かれるようになりました。中国の鳳凰文が時代により表現が変化しているのに対し、日本は時代性があまりなく、他の文様と組み合わせて用いられることもあります。

扇面
Folding fan surface
広げた際、さまざまなモチーフを描くことができるのが、扇文様の楽しいところ。明確な呼び分けのルールがある訳ではないようですが、扇の中に季節の草花や動物、道具や生活用具など器物、幾何学文様などを配したものが「扇面文様」と呼ばれることが多いようです。