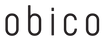■ 唐織|九百錦|花鳥華飛鶴|プラチナ二重箔 ■
この帯に描かれている柄・文様
Japanese patterns and motifs used in this obi

松
Pine tree
1年を通して葉の色が変わらないことから、「常磐木」とも呼ばれる松。平安時代から着物の柄として用いられ、「老松」「若松」「松葉」「松毬」「吹き寄せ」など、現代にも受け継がれる多様な松文様が登場したのは、江戸時代頃からと考えられています

扇面
Folding fan surface
広げた際、さまざまなモチーフを描くことができるのが、扇文様の楽しいところ。明確な呼び分けのルールがある訳ではないようですが、扇の中に季節の草花や動物、道具や生活用具など器物、幾何学文様などを配したものが「扇面文様」と呼ばれることが多いようです。

蝶
Butterfly
歴史のある文様で、奈良時代に中国から伝わり、平安時代に有職文様として公家装束などに取り入れられたところから、広く知られるようになったといわれています。「蝶」の中国語での発音が、80歳を意味する語と同じ音であることから、長寿の象徴とされてきたようです。

牡丹
Peony
幸福、富貴、高貴を象徴する「百花の王」牡丹は、平安時代から着物の紋様として用いられてきました。単体のモチーフだけでなく、室町時代から近世に至るまで多くの人に好まれた、唐草と組み合わせた「牡丹唐草文様」など、さまざまな形で表現されてきた植物です。

唐草花
Chinese flower and plant vines
中国から伝えられた花文様であることから、この名がつけられました。空想の花をモチーフとして飛鳥時代から奈良時代にかけて発達し、5弁から8弁にまとめて和風にアレンジされたのが平安時代頃と考えられています。ベースは円形に構成されたものですが、菱形などさまざまな形状で表現されています。

梅
Plum blossom
奈良時代のはじめに中国から渡ってきた梅は、厳寒の中いち早く花を咲かせることから、忍耐力や生命力を象徴する花として愛好されてきました。学問の神様、菅原道真公が梅の歌を詠んだことから、天満宮の社紋にも用いられています。
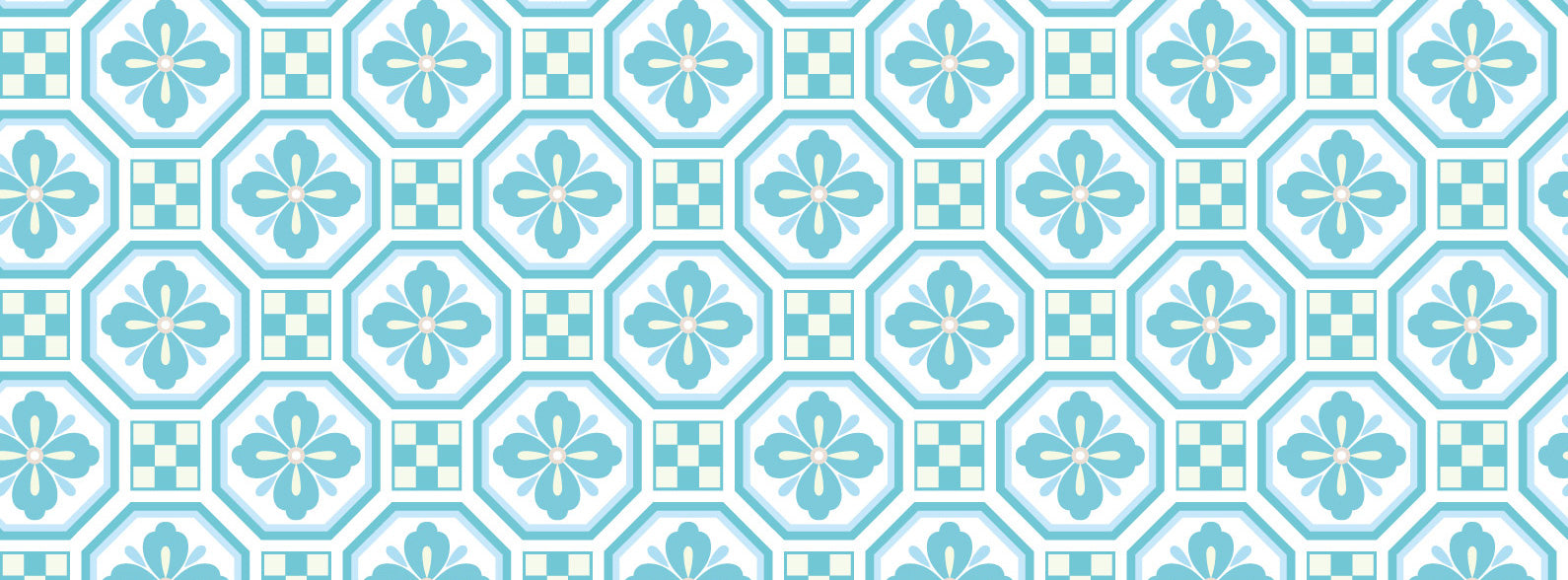
蜀江
Octagonal Square
3世紀頃に中国で栄えた、蜀国の首都を流れていた川の名を冠した割付文様。流域で織られていた赤い地色の錦「蜀江錦」に、原型となる文様が使われていたことから、この名が付けられたと考えられています。
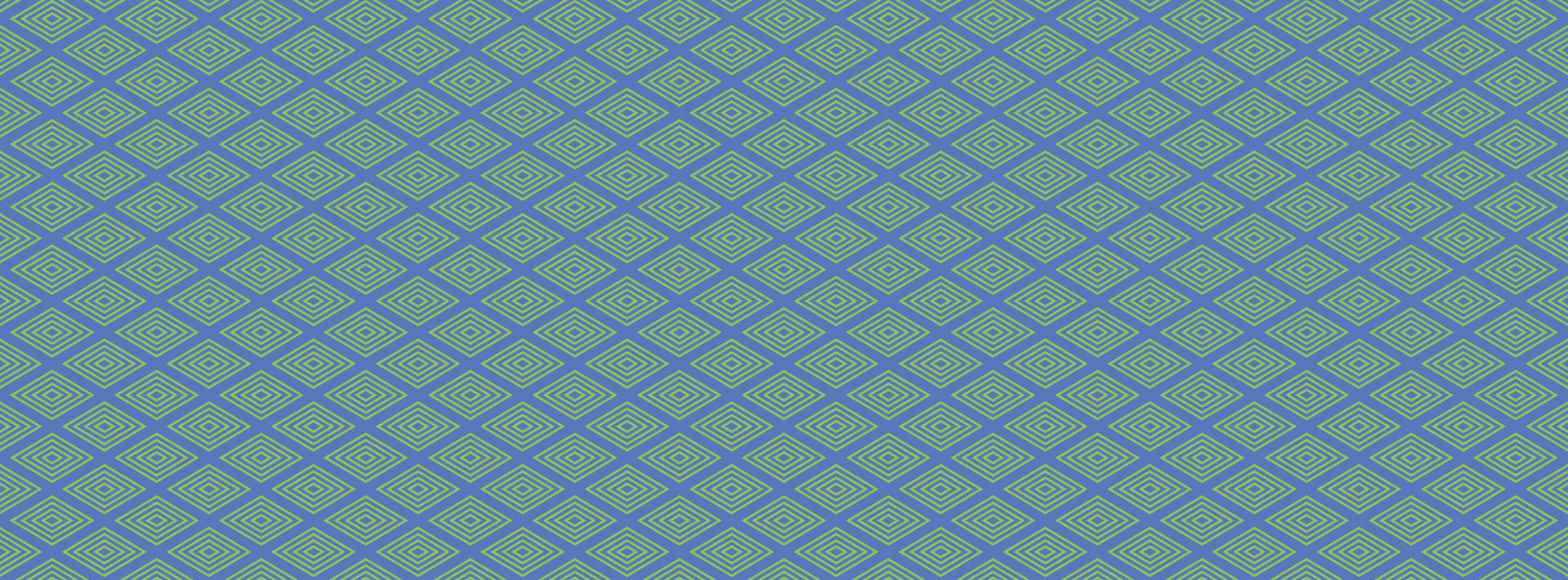
菱
Diamonds
縄文時代の土器にも刻まれるなど古くから描かれてきた文様で、平安時代に有職文様として公家装束に用いられるようになり一気に広まったと考えられています。連続して配した「斜め格子」や「襷文様」、羽を広げた鶴が向かい合い菱形をつくる「向い鶴菱」、4つの菱形で構成された「四菱」など、多様な表現を見ることができます。

青海波
Eternal waves
水面に見える波頭を幾何学的な表現に落とし込んだ古くからある文様で、雅楽『青海波』の装束に用いられたことから、この名が付いたといわれています。