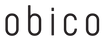この帯に描かれている柄・文様
Japanese patterns and motifs used in this obi

橘
Mandarin orange blossom
『古事記』に不老不死の理想郷に自生する植物と記され、長寿を招き、元気な子供を授かると信じられてきた橘とは、蜜柑のこと。鏡餅の上に蜜柑がのせられるのも、そんな願いからなのです。同様の理由から、婚礼衣装や掛け袱紗などにも多く用いられてきました。

菊
Chrysanthemum
日本の花というイメージが強い菊ですが、奈良時代から平安時代にかけて中国から渡ってきたといわれています。ほどなくして宮中行事に用いられるようになり、南北朝時代には皇室の御紋となりました。格式ある日本の秋の花というイメージは、長い歴史の中で培われてきたものなのです。

菖蒲
Iris
かつては「あやめ」の呼び名が一般的でしたが、葉の形が似ている芳香と厄よけの植物「菖蒲」の字をあててから、この名で呼ばれるようになったようです。杜若とよく似ていますが、花びらの元の部分が白いのが杜若、黄色い筋が入っているのが菖蒲です。

秋草花
Autumn flowers and plants
桔梗、萩、女郎花、撫子、葛、芒、藤袴の秋の七草に、竜胆や菊など、秋の野原に咲く草花を取り混ぜて文様化したものです。七草の中から1種類だけを用いたものを、秋草文様と呼ぶこともあります。残暑が厳しい時期に気分だけでも秋を味わおうという思いから、夏の着物や帯、浴衣などにも用いられてきました。

四季の花
Flowers in four season
はっきりとした四季を持つ日本には季節ごとの美しい草花があり、特に和装においては季節感を身につけることが着こなしの重要なポイントです。一方で、このような四季折々の草花を組み合わせた文様で、季節を気にせず気軽に楽しむのも、和装の一つのスタイルです。

流水
Running water
はっきりとした四季を持つ日本には季節ごとの美しい草花があり、特に和装においては季節感を身につけることが着こなしの重要なポイントです。一方で、このような四季折々の草花を組み合わせた文様で、季節を気にせず気軽に楽しむのも、和装の一つのスタイルです。

紗綾形
The Svastika
桃山時代に中国から伝わった織物「紗綾」の地紋に使われていたことからこの名が付けられた、卍を変形させ連続して配した文様で「万字繋ぎ」と呼ばれることもあります。女性の慶事礼装用の半衿は紗綾形地紋と決められていた頃もありますが、現在は着物や長襦袢の地紋として多く用いられます。